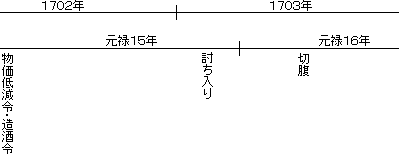日本史は明治以前、すべて旧暦による日付(年月日)で記録されて来た。そしてそれを明治6年になってから全部西洋暦(太陽暦)の年月日に変換し直したわけではない。我々は今でも昔の歴史を旧暦の日付で語っているのである。 ある歴史年表には次のように記されている。 1702 元禄15 物価低減令・造酒令を下す。 赤穂浪士討入り。 しかし歴史的事実は、 1702(元禄15) 物価低減令・造酒令を下す。 1703(元禄15) 赤穂浪士討ち入り。 である。なぜなら物価低減令・造酒令は7月(当然旧暦)のことであるが、ご存知赤穂浪士討ち入りは12月14日のことであり、その日はすでに西暦1703年1月30日であったからである。 また歴史事典を見るとはっきりと 1702(元禄15)年、高家筆頭の吉良義央邸に討入り・・・・翌年2月幕府は一同に切腹を命じた。 などと書いてある。この記述は二重に誤っている。討ち入りの年は1702年ではないし、切腹命令は西暦では翌年ではなく、その年のことであったからである。 参考図 昔の出来事を無理に西暦で表わそうとするとこのような矛盾・破綻が次々と起こる。 旧暦の日付は西暦よりもおおよそ一ヵ月ほど遅れている。したがって旧暦の12月はすでに西暦では年が改まっていると思ったほうが良い。日本史年表の、年号は信じて良いが、西暦は必ずしも正しいとは限らないのである。歴史事典などに西暦・年号対照表が載っていることがあるが、大変危うい。日本史の出来事を西暦で表現したり覚えたりするのには注意が必要なのである。というよりも初めから避けたほうが好ましいのである。 たとえば以下はふつうの日本史年表の旧暦12月の出来事の中からをいくつか抜粋したものであるが、これらの西暦表示はすべてまやかしである。正しくはそれぞれ翌年の数字を記載すべきものである。念のため数字を薄くしておこう。 603
冠位十二階制定
|